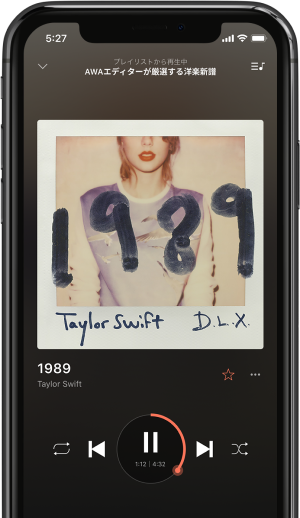- 3:58
- 1:53
- 2:25
- 3:37
- 7:08
- 3:42
- 1:16
- 3:27
説明文
クラッシック音楽になじみのない方も何となく聞いたことがある作品のプレイリストです…と毎回書いていますが、今回はそうでないかも知れません。最近、身近に不幸が重なって精神的にダウンした時に聞きたくなった、「悲しい気持ちに寄り添ってくれる」と思う曲を個人的な感覚で集めてみました。そのため、これまでのプレイリストのように聞いたことがある曲ではないかもしれませんがご容赦ください。気持ちが沈んだ時の回復法として、あえて暗い曲調の音楽を聴いて思いっきり暗くなってみることも効果的です。そんな時に手助けとなるリストだと思います。
#1 フレデリック・ショパン作曲 夜想曲第20番嬰ハ短調 B49 「遺作」
遺作というタイトルになっているが、実際はショパンが20歳の1830年に作曲された作品。発表されたのはショパン没後25年が経過した1875年。また夜想曲(ノクターン)とされているが、初めはアダージョというタイトルで、ショパン自身はノクターンと命名しなかったと推測されている。故郷のワルシャワを離れウイーンで演奏会を開くも、人々に全く受け入れられず、失望と焦りを繰り返す毎日の中で作曲された曲。悲しみを伴う美しい旋律が印象的。映画「戦場のピアニスト」で使用された。
#2 レモ・ジャゾット作曲 アダージョ ト短調 (アルビノーニのアダージョ)
ジャゾットは1910年生まれのイタリアの音楽学者。音楽評論家として活躍しており、その活動の中でバロック時代のイタリアの作曲家アルビノーニの系統だった作品目録を作成したことで名高い。ジャゾットは当初、このアダージョをアルビノーニの旋律を基に編曲したと言っていたが、現在では完全に彼の作曲した作品であることが判明している。オルガンと弦楽器が奏でる、切なく感傷的な旋律が印象的な作品。日本映画「ソロモンの偽証」などの伴奏音楽・テーマ曲として使用されている。
#3 ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル作曲 ハープシコード組曲第2番HWV437 第4曲「サラバンド」
「サラバンド」とはスペイン起源で、17,18世紀にヨーロッパの宮廷で流行したゆるやかな速度の3拍子の舞曲のこと。ヘンデル作曲のこの曲は優雅でありながらも深い情感を持ち、バロック音楽を代表する精妙な表現の曲。日本映画「剣岳 点の記」や2025年夏の金鳥のCMなどでも使用されている。余談だが、宮崎駿監督のジブリ映画「風の谷のナウシカ」で流れる「ナウシカレクイエム」の一部(ラン・ラララ…の前の部分)がこのサラバンドとそっくりであり、一時期パクリ議論がクラッシック音楽界隈を賑わせていた。
#4 ウラディーミル・ヴァヴィロフ作曲 「カッチーニのアヴェ・マリア」
グノー(バッハ)、シューベルトの作品と並ぶ世界3大アヴェ・マリアと評されている曲。他の作曲家のアヴェ・マリアと比較し、悲しみの要素が強く表現されている作品。ジュリオ・カッチーニはルネッサンス末期からバロック初期のイタリアの作曲家であるが、この作品はロシアの作曲家、ギター・リュート演奏家であるウラディーミル・ヴァヴィロフが20世紀になって作曲した。彼は自身の作曲した曲を有名な作曲家(主にルネッサンス&バロック期)の作品として発表することが多かったとのこと。ゆったりとした旋律とシンプルながらも心に響く和声が特徴で、聞く人の心を静かに包み込むような魅力のある曲。
#5 サミュエル・バーバー作曲 弦楽四重奏曲第1番 作品11 第2楽章 弦楽のためのアダージョ
アメリカの作曲家サミュエル・バーバーが1936年に作曲した弦楽合奏のための作品。一般的に「バーバーのアダージョ」と呼ばれている。すすり泣くような旋律や中間部終わりの激しく突き上げる慟哭のようなクライマックスが特徴的な作品。この曲は1963年に亡くなったアメリカのジョン・F・ケネディ大統領の国葬で使用され有名になった。その後個人の葬儀や慰霊祭などで定番曲として使用されるようになったが、バーバー自身は生前「葬式のために作った曲ではない」と不満を述べていたとのこと。
#6 ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲 レクイエムニ短調 K.626 第8曲「ラクリモーサ(涙の日)」
「レクイエムニ短調」は1791年にモーツァルトが作曲した死者のためのミサ曲。この作品は一般的にヴェルディ、フォーレの作品とともに「3大レクイエム」と呼ばれることが多い。この作品はモーツアルトの絶筆となったものであり、全14曲のうちそのほとんどが未完。この第8曲「ラクリモーサ」をはじめその多くが弟子のジュスマイヤーの補筆となっている。とはいえ、モーツァルトの傑作の一つとして演奏されることが多い。ショパンやJ.F.ケネディの追悼ミサでも演奏された。1984年の映画「アマデウス」の中でも効果的に使用されている。
#7 オットリーノ・レスピーギ作曲 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲 第3楽章 シチリアーナ
イタリアの作曲家レスピーギが1932年に作曲した3つの組曲で全12曲からなる組曲。いずれも古いリュート(ギターの先祖のような楽器)のための曲を、現代のオーケストラないし弦楽合奏のために編曲したもの。その中でもこの第3組曲のシチリアーナが最も有名であり演奏される回数も多い。イタリアの近代以前の時代への郷愁をまるで印象派の絵画のような美しさによって表現している。個人的には弦楽器が高音で叫ぶような旋律が大好きで、小学生の頃から好んで聞いていた曲。
#8 ローウェル・メイスン編曲(原曲不詳) 讃美歌第320番「Nearer My God to Thee(主よみもとに近づかん)」
アメリカの作曲家メイスンが古くからの民謡を基に書き起こした曲で讃美歌の一つ。教団、会派によって歌集番号や歌詞がことなる。古くから世界中で親しまれている旋律で、多くの芸術作品で使用されている。映画「タイタニック」ではタイタニック号が沈没する場面でバンドメンバーの最後の演奏、アニメ「フランダースの犬」では最終回に、主人公ネロとパトラッシュを天使が迎えに来るシーンで使用されている。
今回は暗めの曲ばかりのプレイリストになっているので、最後は穏やかな讃美歌を選びました。
…もっと見る