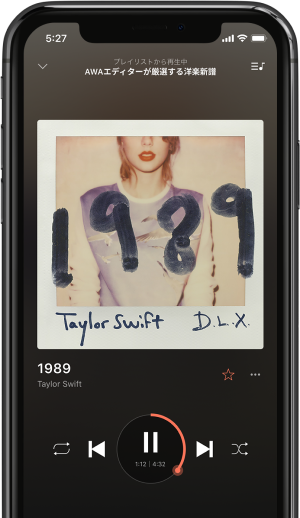- 4:29
- 5:13
- 3:53
- 3:45
- 4:37
- 4:10
- 5:29
- 3:47
説明文
“ 地道にいこうよ ”
目の前の出来事に瞬間的に反応し
一喜一憂しすぎないようにしようね
間違った結論を出しやすくなるから
話を聞いたり本を読んだりする時は
まずは感情やバイアスを控えて、抑えて
何を言っているのか、何が書いてあるのか
なるべく正しく理解するよう心がけよう
感情は、後から乗っけた方がいいんだよ
完璧なんてない
ずっとそこへ向かい続けるだけ
どんな人でも
始める時は当たり前に中途半端なものさ
そして教えを請う勇気が大切なんだ
自分の誤りを認めることは
今までの自分を
否定することではないんだよ
これを誤解してしまうと
まったく成長できなくなってしまう
せっかく失敗や間違いをしたのなら
恥ずかしがるのは少しだけにして
そこから学べることを探してみよう
あとは、自分が感じたこと、思ったこと、
考えたこと、そのくらいはちゃんと
言葉にして伝えられるよう地道にいこうよ
-----
“ 少し考えを深めてみる ”
過去の出来事を思い出に変えられず、長く引きずってしまう人は少なくありません。
その多くは、その出来事に対して納得や解決ができていないからです。
では、なぜ私たちはそのことを深く考えず、立ち止まってしまうのでしょうか。
それは、「考える」という行為が、自分の弱さや不完全さ、そして不確かな未来と向き合うことだからです。
思考には痛みが伴います。だからこそ、私たちは無意識のうちにそれを避けようとするのです。
けれど、その恐れの正体を見つめることこそが、前に進むための第一歩。
そのためには、まず自分の感情を丁寧に、静かに分析することが必要です。
---
外側から内側へ——コントロールの転換
心が不安定なとき、人は外の世界を過剰にコントロールしようとします。
それは、内面の揺らぎを覆い隠し、一時的な安心感を得ようとする防衛反応です。
- 他者評価をコントロールしようとする
「嫌われたくない」「馬鹿にされたくない」という恐れから、他人の言動を予測し、操作しようとします。
しかし、他人の心は思い通りにはなりません。期待が外れたとき、深い痛みが生まれます。
- 結果をコントロールしようとする
失敗への恐怖から、完璧な結果を求めてあらゆる要素を操作しようとします。
けれど、結果には偶然や運が絡むため、些細な失敗でも自己否定につながってしまいます。
一方、心が安定している人は、外部ではなく自分の内面に意識を向けます。
彼らは感情を分析し、「変えられるもの」と「変えられないもの」を見極める力を持っています。
- 他者評価ではなく、自分の行動に焦点を当てる
「どう思われるか」ではなく、「どうありたいか」に意識を向けることで、他人の言動に振り回されなくなります。
- 結果ではなく、過程に集中する
結果は運に委ね、自分ができる努力の過程に集中することで、結果に左右されず、自己肯定感を保てるようになります。
この視点の転換こそが、心の安定を築く鍵なのです。
---
「考えるのが怖い」という感情を見つめる
「考えるのが怖い」と感じるとき、そこには複数の痛みが絡み合っています。
- 自己と向き合う痛み
自分の弱さや欠点に直面する苦しみ。
- 現実と向き合う痛み
変化のために必要な努力や困難を想像する辛さ。
- 不確実性と向き合う痛み
「答えが見つからないかもしれない」という不安から、思考そのものを放棄してしまうこと。
しかし、これらの感情に気づき、言葉にすることは、恐怖を乗り越えるための大きな一歩です。
「怖い」と自覚できた瞬間、あなたはすでに「思考を止めている自分」を認識しています。
その気づきこそが、負のループを断ち切る糸口になるのです。
---
感情を分析する習慣を育てる
過去を引きずるループから抜け出すには、自分の感情を分析する習慣を育てることが不可欠です。
たとえば、「なぜ今、考えるのが怖いと感じるのか?」と自問してみましょう。
その感情を丁寧に言葉にすることで、恐怖の原因が明らかになり、コントロール可能な部分に意識を向ける力が育ちます。
こうした小さな習慣が、思考への恐怖を和らげ、心の安定を築く土台となるでしょう。
そして何より——感情を分析するという行動こそが、過去と向き合い、未来へ進むための、最も力強い解決策なのです。
…もっと見る