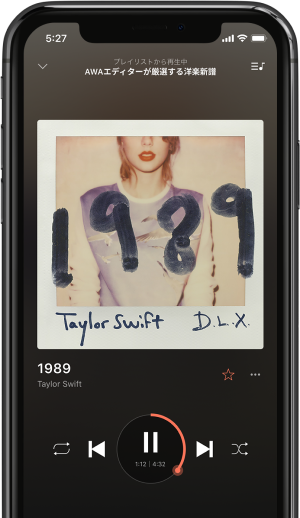- 6:01
- 1:49
- 4:02
- 4:14
- 2:54
- 3:31
- 1:27
- 2:53
説明文
クラッシック音楽になじみのない方も何となく聞いたことがある作品のプレイリストです。今回は眠い春にピッタリの「睡眠導入効果が期待できるクラッシック音楽」をリストアップしました。個人的な感覚で選曲しましたので、いろいろとご意見あるでしょうがご容赦ください。
#1 ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲 管弦楽組曲第3番ニ短調 BWV1068「G線上のアリア」
「G線」とはヴァイオリンの4本の弦の中で一番太く再低音を奏でる「第4弦」のこと。原曲をヴァイオリニストのヴィルヘルミが、G線だけで演奏できるヴァイオリン曲に編曲したため、この名前で呼ばれるようになった。とてもゆったりしたアダージョのテンポで演奏され、ヴァイオリンの柔らかい音色と優しい旋律が心を落ち着かせてくれる、赤ちゃんの寝かしつけにも使用される曲。
#2 ロベルト・シューマン作曲 「子供の情景」作品15 第1曲 「見知らぬ国々」
シューマンが妻クララに宛てた手紙の「あなたは時々子供に思えます」というフレーズの余韻の中で作曲した30曲ほどの中から、12曲を選んだ曲集「子供の情景」の中の第1曲。第7曲の「トロイメライ」も今回のテーマにピッタリの曲ですが、こちらの曲も優しい曲調で、睡眠導入にはオススメなのでぜひお聞きください。
#3 ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲 カンタータ第147番「心と口と行いと命」より「主よ人の望みの喜びよ」
バッハが教会の音楽監督に就任した時に、讃美歌「イエス、わが魂の喜び」の詩節をもとに作曲した曲。イエスキリストの誕生や救いの恵みをたたえる内容。穏やかで美しい旋律から落ち着いて眠りにつける楽曲。ちなみに今回リストした清塚信也の演奏は、常にAWAクラッシックの上位に位置している曲。
#4 フリードリヒ・フライシュマン作曲(もしかしたらベルンハルト・フリース作曲かも) 「モーツァルトの子守唄」(邦題:眠れ良い子よ)
ブラームスの子守唄(#5)、シューベルトの子守唄(#6)と並び「世界三大子守唄」と呼ばれる作品。モーツァルトの遺品の中からこの子守唄の楽譜が発見されたことから当初モーツァルトの作品と思われていたが、図書館の資料にベルリンの医師フリースの作曲と書かれたものが発見され、その後フリース作曲が定説となっていた。しかし最近の研究では旧ドイツにあったザクセン・マイニンゲン公国の宮廷音楽家フライシュマンのバージョンがオリジナルであると言われている。日本では作曲家の堀内敬三の訳詞「ねむれ良い子よ庭や牧場に」で歌われている。この歌い出し部分がこの曲の邦題。原題の直訳は「眠れ、私の王子さま、眠ってね」。
#5 ヨハネス・ブラームス作曲 「ブラームスの子守唄」作品49-4
友人の女性に子供が生まれたことを記念して作曲された。「5つの歌曲」のうちの1曲で、モーツァルト、シューベルトの作品と並ぶ3大子守唄。心が安らぐ素朴な旋律、ゆりかごを思わせるシンコペーションを伴った音型、落ちつきを表す低音など、子供だけでなく大人が聞いていても眠ってしまうような優しい作品。
#6 フランツ・シューベルト作曲 「シューベルトの子守唄」D498 作品98 第2番
モーツァルト、ブラームスの作品と並ぶ三大子守唄。シューベルトはこの曲を19歳の時に作曲した。過去の統計によると、日本においては3大子守唄の中で一番歌われている曲とのこと。内藤濯の「ねむれねむれ母の胸に」で始まる訳詞が有名。大きな愛で包み込むようなメロディーが心に安らぎをもたらせてくれる作品。
#7 ヨハネス・ブラームス作曲 「15の子供のための民謡集」第4曲「眠りの精」
ドイツ民謡集からブラームスが編曲した「15の子どものための民謡集」の第4曲。「眠りの精」とはドイツなどの国の民話によく登場する「砂の精」のこと。夜に子供たちの目に砂を撒き眠くさせる妖精。ブラームスが親しかったロベルト・シューマンが亡くなった後に、その遺児たちのため、ピアノ伴奏に編曲して贈ったとのこと。作品のテーマからも子守唄としてピッタリの、睡眠導入にはオススメのクラッシックです。
#8 ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲 「アヴェ・ヴェルム・コルプス」ニ短調 K.618
モーツアルトが妻コンスタンツェの療養を世話した合唱指揮者アントン・シュトルのために作曲した混声四部合唱の作品。「アヴェ・ヴェルム・コルプス」とはカトリックで用いられる聖体讃美歌で「めでたし、まことのお身体」という意味。「レクイエム」と並ぶモーツアルト晩年の傑作とされ、合唱と弦楽にオルガンのみというシンプルな編成で、長さも46小説、演奏時間約3分半という作品。悲痛な「レクイエム」と比較すると、すべての闘いを終えて天に帰ったようなやすらぎに満ちている作品。とにかく美しく優しい曲調なので、Good nightの作品としてはオススメです。
…もっと見る